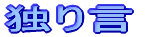
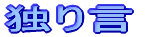
このページには、いわゆるジャーナルを掲載します。
リンク・ページ「芝居」と「推理小説」では、一人の鑑賞者としての勝手な思いを書きつづってみます。
評論家でもエッセイストでもない者がこんなことを公表できるとは、インターネットとはありがたいメディアです。
このホームページで開設者本人が一番楽しんでいるのは、このリンク・ページかも知れない。
いずれの分野も「好き嫌い」の世界ですから、来訪者の意に添わなくとも、ご勘弁願いたい。
「芝居」で取り上げるのは、11代目団十郎など、主に1970年頃の古い話題です。
「推理小説」のマニアとして自分自身をランク付けすると、「中の下」か「下の上」といったところか。
松本清張と宮部みゆきは一通り読んでいるが、赤川次郎、西村京太郎、内田康夫は読まない。
「綾辻以後」にも興味ない。
ホームズとルパンは小学校以来、何年かおきに読み返して楽しんでいる。
![]()
2025年6月27日(金)win11パソコン
新発売のホームページビルダー23のシリアルナンバーなどを記載した書類が昼過ぎに届いた。早速、手順通りにインストールし、アイコンをクリックしたが、「ナニヤラが見つからないため続行できません」と出た。ネットからインストールしたソフトが動かないとは、初めての経験である。来週以降、サポートに問い合わせるしかない。当分、win10パソコンを使い続けることになりそうだ。
2025年6月26日(木)近大眼科
朝早くに近大病院へ。視野検査の結果は変わらずだし、眼圧も芳しくない。目がまともに見えているうちに、成すべきことを成さねばならないと、改めて思った。
2025年6月25日(水)散髪
朝、散髪のために外出。終了後は明日の通院に備えてそのまま帰宅。それだけのことなのに、帰宅後は疲れて何もできない。運動らしいことはバス停までの往復だけなのに、我ながら情けない。
2025年6月23日(月)近大眼科
朝早くに近大病院へ。7時半から番号札の発行、8時から対面の受付というシステムを初めて知った。本日は9時から1時間ほどの視野検査だけ。帰宅途中、金剛駅前や河内長野駅前で書店や食堂に寄ったためか、夜、就寝してから左足が繰り返し痙攣したのにはまいった。
2025年6月21日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。本日も帰宅後は疲れ切って何もできない。
2025年6月20日(金)キールマイヤー研究
ここ連日、新ガラケーとwin11パソコンの設定に時間を取られ、文献に接していない。本日は断固として文献を読むことにして、英文の『キールマイヤー論集』(2021)の第2章、カンツ(Kai
Torsten Kanz)による「キールマイヤーの名声と運命」(Kielmeyer’s fame and fate)に取り組んだ。著者はドイツにおけるキールマイヤー研究の中心人物であり、本章はキールマイヤー研究の現状を総括する内容になっている。
キールマイヤーには研究論文といえるものが無に等しかったが、それにもかかわらず優れた科学者として評価されていたという。有名な1793年講演録は論文ではなく、内容も科学上のオリジナルな研究ではない。当時の学界ではすでに「書くか死ぬか」(publish or perish)の原則が確立していたのに、業績皆無のキールマイヤーがなぜ高く評価されていたのか、納得できる理由は示されていない。
キールマイヤーは「ドイツ自然哲学の父」、あるいは「生物発生原則の創始者」、あるいは「生物学の父」と呼ばれることがある。それぞれ、必ずしも間違いとはいえないが、一面的に過ぎる。キールマイヤーはより総合的に理解されるべきである。そのためには、キールマイヤーの未公刊資料がさらに刊行されなければならないという。
本書にはトレフィラヌスの名はない。しかしトレフィラヌスがキールマイヤーから大きな影響を受けていたことは間違いないと思う。我がトレフィラヌス研究の中ではかなりキールマイヤーについて論じなければならない。それならむしろ、独立した「研究ノート」として「キールマイヤーの生涯と業績」をまとめておこうかと思う。トレフィラヌス研究がまとまるにはまだまだ時間がかかるので、前もって「キールマイヤーの生涯と業績」を書いておくことは「書くか死ぬか」の原則にも適合するだろう。
2025年6月15日(日)win11パソコン
中古win11パソコンの活用に取り組み、現行のwin10パソコンとほぼ同様に使えるようになった。ただ、win11に対応したホームページビルダーをインストールする月末まではwin10パソコンを使い続けることになる。
ここで問題になるのは、「一太郎」で作成した大量の文書である。再利用の可能性のない事務的な文書類は廃棄してもよいだろう。再利用の可能性のある論文原稿などはテキスト化して保存しようと考えている。
2025年6月14日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。本日も帰宅後は疲れ切って何もできない。NHKBS夜9時からのドラマ「天城越え」。清張の名作短編がどのように映像化されるか、興味はあったが、眠気には勝てなかった。
2025年6月13日(金)win11パソコン
しばらく放置していた中古win11パソコンの活用に取り組む。Microsoftアカウントのことなど、慣れた人には簡単だろうが、その確認に時間を取られた。Officeも無事、インストールできたようだ。ただし、パソコンを切り替えるには、まだまだ時間がかかりそうだ。
2025年6月9日(月)ガラケー更新
使用中のガラケーの使用期限が来年の3月。数年前から繰り返し、スマホへの変更を勧めるドコモの文書が届いているが、ほとんど外出しない自分にはスマホの必要がない。これまでと使い勝手の変わらない二つ折りのガラケーを電話で注文し、今朝、それが届いた。
まず、電池を取り付けて充電を始めたが、終わったのが夕刻。simカードを取り付けて初期設定を試みたが、うまくいかない。結局、夜になってサービスセンターに電話して利用できるようになった。ガラケーといっても1Gのスマホ機能が入っているらしい。せっかくだから、そうした機能にも挑戦しようと思う。我が寿命を考えれば、おそらくこの機種を更新することはないだろう。
2025年6月8日(日)体調回復
雨模様の一日だったが、朝は団地自治会主催の溝掃除。昼前にシニアカーで隣町のスーパーへ。帰宅後もけっこう、体が動いた。まともな体調にもどったようだ。
2025年6月7日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。帰宅後は疲れ切って何もできない。ここ数日、体調不良というほどではないが、疲労感が大きく、家事以外、何もできないでいる。この状態は一時的なことで、続くことはないと願っている。
2025年5月31日(土)デイサービス。中古パソコン入手
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。欠席者が多いのは天候不順のためか。帰宅後の午後にクロネコヤマトで中古パソコンが届いた。早速、電源を入れてみる。無事、起動。まずはネット接続を試みる。ルーターのボタンを押すだけの作業にたどり着くのに、ずいぶんと無駄な時間を過ごしてしまった。次はWindows11を使いこなし、データやアプリを移行しなければならない。いずれについても参考資料を取り寄せ、慌てずに取り組んでいきたい。
2025年5月30日(金)中古パソコン発注。内科医
午前中に中古パソコンをBeStockに発注。いつまでも迷っていられないので、2万円台のwin11パソコンを発注した。その後、昼前に隣町の福岡内科へ。降圧剤を受け取ってからスーパーへ。これで本日のエネルギーを使い果たした。
2025年5月29日(木)竹本碩太夫
朝日新聞夕刊に碩太夫(ひろたゆう)の紹介記事が大きく掲載されていた。1995年生、2017年千歳太夫に入門。小学生の時から文楽を追いかけていたという。すごい感受性の持ち主だと思う。文楽の出演者の名前と顔を憶えるように努めているが、碩太夫クラスの太夫を憶えるのは難しい。しかしこの記事でしっかり頭に入った。今後の成長を見守っていきたい。
ここで思い出したのが中井美穂『12人の花形伝統芸能』( 2019)で紹介された三人、竹本織太夫、三味線の鶴澤清志郎、人形の吉田玉助。三人とも中堅として文楽を支えている。今年の「夏休み公演」第三部の「小鍛冶」ではこの三人が中心になっている。碩太夫が第二部の「桂川」の「道行」に出るだけなのはやむを得ないだろう。
2025年5月28日(水)奈良国立博物館「超国宝」
散髪に外出したついでに、奈良博特別展「超国宝」後期展示へ。新たに清凉寺の釈迦如来立像や中宮寺の菩薩半跏像が出ているが、なにしろ前回(4月30日)を上回る大混雑。人ごみの中にぃるだげで疲れてしまう。とても仏様たちの声を聴く余裕はない。仏像館に寄る気力も失せ、早々に引き上げた。今後、混雑する展覧会は避けなければなるまい。
2025年5月25日(日)中古パソコン
ここ数日、ネット上でwin11の中古パソコンを探すのに時間を取られている。現在利用しているwin10パソコンは川上キカイから1万円で購入し、問題なく動いてきた。残念ながら現在、川上キカイは個人客への販売をしていない。アマゾンで最安値のものに決めかけたが、ネット上の評判があまりに悪いので中止した。安価な中古パソコンにofficeが入っているのが不思議だったが、業者が不正に入手したものであることも知った。どうやら2万円台で自分の用途に適合したものが購入できるようだ。まだ慌てる必要はないが、近日中に発注しようと考えている。
2025年5月24日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。暑苦しい日々が続いていたが、一転、寒さを感じるほどになった。体調維持が難しい。
2025年5月23日(金)整形外科医
朝早くにバスで三日市町駅筋の田中整形へ。隣の薬局で骨粗鬆症の薬を受け取り、郵便局に寄ってから帰宅。これだけのことで疲れ切ってしまった。
2025年5月19日(月)スーパー買い物
朝、体調は良く、疲れも抜けたと感じた。昼前にシニアカーで隣町のスーパーへ。しかし帰宅後はぐったりして何もできない。いつものことだとあきらめよう。夕食後、ようやく気力、体力が回復してきたので3日分のジャーナルを書いている。
2025年5月18日(日)体調不良
昨日の疲れが抜けない。終日、ぼんやり過ごすしかない。
2025年5月17日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で2週間ぶりの運動機能訓練。いつもと同じメニューをこなしたが、帰宅後の疲労感がはるかに大きい。この2週間、体調悪化を恐れて家でも運動を控えていたためであろう。
2025年5月16日(金)トレフィラヌス研究
4日前に『生物学』第3巻(1805)の後半、第4編「生物の生殖、成長、および衰退」の第1部「生殖」(Erzeugung)の第1章(pp.231-255)を読了。章題には「生殖方法の分類」とあるが、それを扱うのは章の最終3ページになってからで、章の大部分は哺乳類の子宮の構造をハラー『人体生理学原理』に基づいて詳細に語ることに費やされている。生殖方法としては、現在の用語でいえば、有性生殖の生物、無性生殖の生物、および有性生殖と無性生殖とを併用する生物の3クラスに分けており、それぞれを第2章、第3章、および第4章で扱っている。著者の意向としては、自然史体系化の締めくくりに種を維持する生殖、さらにそれに続く成長と衰退を論じたのであろう。
この第3巻(1805)までに自然史の体系化という作業が完結しているといえよう。その作業の前提になっているのが、生物進化説、発生の後成説、および下等生物の自然発生説である。ところが、自然史(分類、分布、化石)の資料をあまりにも詳細に記載しているため、この著者の先進的な見解が埋もれてしまっている。最初からこの前提を明記し、資料の記載を大幅に簡潔化したならば、本書は大きな反響を呼び、科学史家から無視されることもなかったろう。
第4巻(1814)以降は生理学的内容を扱っている。第4巻には第5編「栄養」(Die Ernährung)が収められ、主として動物の呼吸器、循環器、および消化器を解説している。第3巻(1805)の第4編最終ページ(p.593)には、「次の巻では栄養の問題を扱う」と記載されており、第4巻以降で生理学的内容を扱うのは初期段階から著者の構想にあったのだろう。第3巻(1805)から第4巻(1814)までに9年も要したことについては、第4巻の「まえがき」で、著者の生活環境の激変によるものであると述べている。
「生物学」という新しい学問分野を樹立しようとしたとき、その具体的内容としては既存の「自然史」と「生理学」とを合体させることしか思い浮かばないのではなかろうか。ただしトレフィラヌス『生物学』の場合、第5巻(1818)では著者の顕微鏡観察が、第6巻(1822)では医師としての著者の経験が前面に出ており、新分野の樹立という本来の趣旨からしだいに遠ざかっているように思える。
とにかく、トレフィラヌス『生物学』のおおよその全体像がつかめたので、同書の読解は一旦、中止し、これまでのところを整理しておきたい。ハラーの生理学に目を通す必要もある。ダウンロードしたままになっている学位論文も読んでおきたいと思う。
2025年5月15日(木)文楽・新聞劇評
朝日新聞夕刊に文楽5月東京公演の劇評が掲載されていた。第二部の「義経千本桜・二段目」について、「切場では、錣太夫・宗助にスケールの大きさと品格が欲しい」とある。むべなるかな。さもありなん。4月大阪公演の第一部「義経千本桜・二段目」の切が千歳太夫なら出かけるつもりでいたが、錣太夫と知って止めたのは正解だった。ところで、東京の文楽公演は「国立劇場閉鎖で逆境にある」、「国立劇場が老朽化し、再整備の目処も立たない」という。日本、日本と騒ぎ立てる保守系の政治家たちも、日本固有の文化には無関心なのだろう。情けない。
2025年5月11日(日)トレフィラヌス研究
朝、起床すると風邪が抜けた感じがした。不調を感じてから丁度1週間。自然治癒したと思いたい。
気力も回復し、『生物学』第3巻(1805)の第4編「生物の生殖、成長、および衰退」に着手できた。その大部分は生殖(Erzeugung)についての議論である。発生の後成説と進化論を奉じる著者は、当時としては当然のことながら、下等生物の自然発生も容認しているが、それについては第2巻の第2編で扱ったので、ここでは同種の生物による生殖を扱うという。第4編の序論部分を読むと、第1巻から第3巻までは一貫した方針で執筆され、もともと著者が「生物学」として想定した内容はそこまでであったと思われる。
今はとにかく、第4編の読解に集中したい。
2025年5月10日(土)体調不良
体調が回復していないのでデイサービスは休んだ。といって、文献に取り組む気力もない。テレビとパズルで過ごす日々が続いている。
2025年5月7日(水)トレフィラヌス研究
『生物学』第5巻(1818)の第8編「神経系概論」第1部の最終部分に目を通す。前段から引き続いて脳と神経系の構造を論じており、ここでは下等動物のそれを比較検討している。差し当たり、克明に解読する必要ないだろう。
『生物学』の第1巻(1802)・ 第2巻(1803)・ 第3巻(1805)と
第5巻(1818)・ 第6巻(1825)とはかなり性格が異なっていると思われる。第3巻までは自然史の成果を著者の立場で体系化しているが、第5巻・ 第6巻では未成熟な分野について著者自身の研究をもとに論じている。第3巻までは生物学概論として妥当な内容だが、第5巻・ 第6巻はそこから逸脱しているのではなかろうか。第4巻(1814)がどちらの性格に近いかは、読んでみないと分からない。
2日前の5日(月)から体調不良が続き、市販薬で症状を抑えている。日常生活は通常通りだが、文献に集中するのは難しい。テレビとパズルで過ごしている。
2025年5月4日(日)トレフィラヌス研究
1週間ぶりに『生物学』第5巻(1818)の第8編「神経系概論」第1部を読み続ける。脳、脊髄、末梢神経の構造についての議論が続く。著者自身も顕微鏡観察を実施しているが、その能力は疑わしい。脳は葉状構造であり、繊維構造は認められないという。脊髄の中を貫通する繊維構造
があるという研究報告に対し、新鮮な試料ではそのような構造は認められず、薬品処理によって人為的に表れるだけだという。当時の神経系研究の混乱ぶりを反映しているともいえよう。この後(pp.327-335)、神経節(ganglia)についての諸説が紹介されるが今は省略し、第1部の最終部分に進みたいと思う。
2025年5月3日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。本日は帰宅後も体力が残っていたようだ。
2025年4月30日(水)奈良国立博物館「超国宝」
散髪に外出したついでに奈良博の特別展へ。平日なのに期待に反し、正倉院展なみの混雑であった。仏教関連の逸品が集められているが、仏像に焦点を当てて見てきた。法隆寺からも数点の出品があったが、注目は「百済観音」。法隆寺ではガラスケースに収められているが、ここでは直に拝見できる。東大寺の「重源上人坐像」は普段、拝観できないので、今回、はじめて接することができた。東京・深大寺の「釈迦如来倚像」もこういう機会がなければ見ることができなかったろう。奈良の山奥まで行って見てきた円成寺「大日如来坐像」も出ている。
常設展の「仏像館」もにぎわってはいたが、特別展ほどではない。「仏像館」の名物である元興寺「薬師如来立像」と館蔵の国宝「薬師如来坐像」は特別展に出ているが、観音様や阿弥陀さんらとゆっくり過ごすことができた。大阪の外に出たのは昨年5月の奈良博「空海」展以来のこと。気にしていた足の異常も再発しなかった。大きな気分転換になったようだ。
2025年4月28日(月)歯科検診
午前の早い時間に隣町の迫川歯科で半年毎の検診。問題なし。ついでにスーパーで買い物。シニアカーで出かけたので雨が心配だったが、午前中は大丈夫だった。本日は帰宅後も動くことができたので、トレフィラヌス『生物学』についてメモ書きを入力することができた。
2025年4月27日(日)トレフィラヌス研究
『生物学』第5巻(1818)の第8編「神経系概論」第1部「神経系の体制についての予備的解説」の読解に着手。この第1部は、「神経系の構成分は脳髄よび脊髄のそれと同じだろうか」
(Was ist das Charakteristische der Nervensubstanz? Ist sie
einerley mit der Substanz des Hirn- und Rückenmarks, oder von dieser
verschieden? p.319) という問いかけから始まる。この文からも分かるように、本書では脳Gehirn)と脊髄(Rückenmark)と神経系(Nervensystem)が並置されている。中枢神経・末梢神経という区別はなされておらず、「神経系」は現在の末梢神経だけを意味している。しかし本文では脳・脊髄についても論じられている。
最初のテーマは脳の髄質の白質と皮質(Rinde)の灰白質との違いである。著者によれば、両者の違いは血管の量の違いであり、皮質には血管が豊富なため色があらわれるという。皮質は脳髄の栄養供給源であるというガルの説は、比較解剖学に基づいて否定している。こうした議論に、当時の神経系研究の限界が見て取れるといえよう。
2025年4月26日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。休憩時の阪神談議は、今のところ楽しい。帰宅後の中継では、なんと巨人に5連勝。まことに、めでたい。
2025年4月25日(金)トレフィラヌス研究
『生物学』第6巻(1822)の第9編「知的世界」第2部(pp.28-63)を一応、読了。前半の中心的なテーマは外部感覚器の誤作動による精神異常、後半は感情のもたらす身体行動への影響である。いずれについても医師である著者の経験が語られている。生物学概論としては逸脱していると思われるが、医師として書き残したかったのだろう。
予知能力についての議論(pp.48-54)や合目的性についての議論(pp.62-63)など、気になるところもあるが、ここで一旦、打ち切り。先に進みたい。第9編の第3部が残っているが、先に第5巻(1818)の第8編「神経系概論」に取り組むことにした。臨床医学的な内容にうんざりしたし、第8編の内容を前提にした議論が第9編にあるからである。本日はまず、その第1部「神経系の体制についての予備的解説」(pp.319-343)をDTAからプリントアウトした。第5巻の巻末には神経系の銅版画も付記されている。生物学らしい内容を楽しみたいと思う。
2025年4月24日(木)内科医
昼前にシニアカーで隣町の福岡内科へ。降圧剤を受け取り、ついでにスーパーへ。これだけで本日分のエネルギーを使い果たした感がある。
2025年4月19日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。帰宅後の疲労がいつもよりはなはだしい。季節外れの暑さのためかもしれない。
2025年4月17日(木)トレフィラヌス研究
『生物学』第6巻(1822)の第9編「知的世界」第2部「動物の有機的諸力に対する心的能力の関係」(Verhältnisse der
Seelenkräfte zu den organischen Kräften der thierischen Natur. pp.28-63)に手こずっている。著者が「生産的構想力」(Die produktive Einbildungskraft)と呼ぶ心的能力が自立的に活動することを幻影による病的行動によって証明しようとしている。その実例としてローマのブルータスとイタリアの詩人タッソ(Torquato Tasso, 1544-95)が登場する。“Ein Trugbild
beschiedden Brutus zum Wiedersehen bey Philippi; mit einem Trugbilde unterhielt
sich Tasso im Kerker.”(p.42). これ以上の説明はない。ブルータスの件はシェイクスピア『ジュリアス・シーザー』第4幕第3場における亡霊のセリフ“thou
shalt see me at Philippi.”によるものと理解できたが、タッソの件が分からない。ネットで調べると、フェラーラのKerkerにある聖アンナ病院での出来事を意味しているらしい。精神を病んだタッソが一時、そこに収容されていたという。ゲーテの作品に戯曲『トルクワト・タッソ』(1790)があるという。当時のドイツの知識人層にはブルータスとタッソの幻影(Trugbild)の件が周知のことだったのだろう。
トレフィラヌス『生物学』は自然史と基礎医学の生理学とを合体させたものといえるが、この第9編第2部はそこから逸脱している。心理学、あるいは精神病学に該当するといえよう。終始、夢遊病(Somnambulismus)について語られているが、医師である著者の体験に基づく夢遊病者(Schlafwandler)の描写は生き生きとしている。「デカルトの悪魔」(p.39)も登場する。著者としては生物学上の重要なテーマだったのだろう。当方としてはあまり興味を持てない内容だが、我慢して読み通すほかない。
2025年4月12日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。
2025年4月10日(木)トレフィラヌス研究
ようやく『生物学』第6巻(1822)の第9編「知的世界」第1部「生物界における心的機能の広がりと階層」(Gebiet und
Stufenfolge des Beseelten in der lebenden Natur)を読了。論文というよりも随想のような記述で、ミツバチやビーバーなど、我々にもおなじみの事例を挙げていく。ヒトの言語能力については、言語が高度な知能の原因ではなく、高度な知能が言語能力の原因であるという(p.10)。結論として著者は、ヒトと動物の心的能力に本質的な差は無いとして次のようにいう。「心的機能においてヒトと動物とには差があるが、両者の類似性を否定するほどのものではない」(In allen diesen Eigenschaften ist zwar der Mensch verschieden von
dem Thier, doch auch nicht so verschieden, daſs alle Aehnlichkeit zwischen
beyden aufgehoben wäre. p.19)。
論考の最終段階(p.24)で、いわゆる発生の反復説が説かれ、次のようにいう。Man hat die Stufen, die der Mensch von seinem Entstehen an bis zu
seiner vollendeten Ausbildung in physischer Rücksicht durchläuft, mit den
allgemeinen Entwickelungsstufen des Thierreichs von den Infusorien an bis zum
Menschen verglichen. この反復説は未読の同書第3巻の第4編で詳細に論じられているはずである。上記の文に続けて、心的能力についても反復説が成立するとして次のようにいう。Es läſst sich eine ähnliche Vergleichung zwischen jenen und diesen
Stufen auch in Betreff der geistigen Kräfte anstellen. 進化論を奉じる著者の立場は明快である。
アリストテレスを繰り返し引用していることなど、さらに検討したいこともあるが、本書の通読を優先し、先に進みたい。
2025年4月6日(日)トレフィラヌス研究
『キールマイヤー論集』第8章のバッハ(Thomas Bach)による論考を読了。論題は「有機体の現象学としての有機体自然学」(Organic physics as a phenomenology of the organic)。18世紀初頭、“physica”は“philosophia
naturalis”と同義で哲学の一部門であり、広く自然物についての理論的考察を意味していたが、18世紀末には“physica”が無生物についての実験科学を意味するようになり、生物は“physica”の領域に含まれなくなった。とはいえ、一部の研究者は生物も“physica”の対象とみなしていた。キールマイヤー1793年講演は“physica”の一分野として有機体を論じたものであった。ただし、結果として「生物学」が独立の分野として成立するうえで大きな役割を果たすことになったという。
キールマイヤー自身が“physica”と名乗っているわけではない。トレフィラヌス『生物学』第1巻(1802)の「序論」(Einleitung)の冒頭では、無生物(die leblose Natur)についての科学が「自然学」(Physik oder
Naturlehre)と呼ばれていると指摘している。著者の主張には疑問が残る。
2025年4月5日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。帰宅、昼食後は疲労でなにもできない。
2025年4月4日(金)トレフィラヌス研究再開
2週間ほど横道にそれていたが、新学期になったことだし(我が身には関係ないが)、そろそろトレフィラヌス研究にもどるとしよう。『生物学』を順序正しく読む必要はないので、本日は最終第6巻(1822)の第9編「知的世界」の冒頭27ページまでをDTAからプリントアウトした。ドイツ語の論文をネット上で読むのは困難だが、プリントに時間を要するのが悩ましい。これと並行して英文の『キールマイヤー論集』(2021)を読んでいきたい。同書の文献欄を見れば、ドイツ語圏ではキールマイヤー研究が盛んであったことが分かる。それに比べてトレフィラヌスはほとんど研究されてこなかったようだ。
2025年4月3日(木)内科医
昼前にシニアカーで隣町の福岡内科へ。降圧剤と整腸剤を受け取り、ついでにスーパーへ。肌寒かったが、満開の桜並木を楽しむには絶好の日であった。
2025年3月29日(土)デイサービス
寒のもどりで、寒い朝を迎えた。しばらく遠ざかっていた電熱チョッキを着用してデイサービスへ。休憩時の話題の筆頭は昨夜の阪神タイガース開幕戦の快勝。みなさん、ご機嫌であった。
2025年3月28日(金)近大眼科
早朝、近大病院へ。あいにくの雨であったが、「春雨じゃ濡れて行こう」程度の小雨。といっても半平太ではあるまいし、本当に濡れるわけにはいかない。「メテに杖つき、ユンデに傘」はけっこう、つらい。しかし帰宅時には雨も上がり、咲き始めた桜並木を楽しみながらのんびり歩いてきた。
眼科での診断では久しぶりに眼圧が一桁になっていた。とりあえず、めでたい。ささやかなながら祝杯を挙げることにした。
2025年3月26日(水)散髪
朝、散髪に外出。暖かさを超えて暑いくらいで、絶好の行楽日和のはずだが、昨日からの黄砂で近くの山もかすんで見える。体調も芳しくないので、遠出をやめてそのまま帰宅。バス停の往復で歩いただけだが、かなりの疲労感で、動くのが億劫である。
2025年3月22日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。複数のスタッフから、昨日、シニアカーで移動中の姿を見たといわれた。午前の部の送車、午後の部の迎車の時間帯と重なっていたのだ。小さな地域内で生活していることの表れでもある。
2025年3月21日(金)青空
朝のうちは寒かったが、日が昇るにつれて春の暖かさがやってきたので、シニアカーで隣町のスーパーへ。久しぶりに真っ青な空を見ながらの移動。青空に語り掛けたくなる気分であった。
2025年3月19日(水)図書返送
朝、樹木や土の上に雪が残っていた。夜の間に雪が降ったようだ。予報士によれば大寒なみの寒さだという。13日に外出した時は電熱チョッキが不用なほど暖かかった。この寒暖差は体にこたえる。
午後、シェリング全集の1冊など桃大図書館から借用していた計3冊をクロネコヤマトで返送した。今回も予めネットで必要事項を入力しておいたので、集荷も簡単に、かつ安価に済ますことができた。
トレフィラヌス研究に一区切りついた気分である。今後は手元の資料を整理し、主目的であるトレフィラヌス『生物学』を全部読むという作業を進めなければならない。ただし、しばらくは横道にそれるのもよいだろう。
2025年3月18日(火)トレフィラヌス研究
シェリング『自然哲学体系への草案序説』(1799)の邦訳(後藤正英訳)を読了。原書は84ページの小冊子で、その全てが訳出されている。全6章から成り、初めの5章で「自然哲学」の意義を論じている。自然哲学は超越論的哲学の観念論的な説明を排し、「徹頭徹尾、実在的。p.207」(ganz und durchein realtisch. 旧全集Ⅱ274)であるという。自然は自立した存在とされ、その自然についての事実は実験科学、すなわち、「経験的自然学」(empirische Physik)によって明らかにされる。その事実を基に自然を深く理解するのが自然哲学、すなわち、「思弁的自然学」(Speculative Physik)であるという。
その思弁的自然学の内容が本書の大部分を占める第6章「思弁的自然学の体系の内的構成」で語られる。すでに第2章の冒頭で自然哲学は「自然学のスピノザ主義」(der Spinozismus der
Physik. Ⅱ274)とあるように、第6章ではスピノザの「能産的自然・所産的自然」(Natura naturans. Natura naturata)の概念に基づく議論が展開される。Richards(2002)が指摘しているように、結局は超越論的議論になっているように思える。流し読みで理解できるような内容ではないが、トレフィラヌスへの影響を考えるうえでは気にしなくてもよいだろう。ただ一点、注目したいのは自然の階層性である。無機的自然には磁気、電気、化学過程という階層があり、有機的自然には感受性、興奮性、形成衝動という階層があるという。ここにもキールマイヤーの影響が歴然としている。
トレフィラヌス『生物学』の背景を知るためにシェリング自然哲学に取り組んできたが、ここで一旦、打ち切って先に進みたいと思う。
2025年3月14日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。
2025年3月13日(木)大阪市立美術館「リニューアルオープン記念展」
昼過ぎに大阪市立美術館へ。2年半の改修工事を終えて何が変わったか。館内に入るだけなら無料で、売店やカフェも利用できる。そのため、1階と2階、計4室の展示場に入るにはいちいち観覧券を提示し、入室済の印が押される。ざっと全体を見てから焦点を定めてゆっくり見て回るといった方法はとれない。あらかじめ出品リストを見て、どの展示室に重点を置くか決めておく必要がある。
今回は館蔵の中国と日本のさまざまな作品が展示されている。注目すべきは、2階第4会場の「住友コレクション」16点の日本画であろう。大阪市立美術館の「住友コレクション」とは1943年に住友本社の後援によって大阪市立美術館で開催された「関西邦画展覧会」のために制作された20点の日本画コレクションで、翌年に同館に寄贈されたものとのこと。当時の京都・大阪を中心とする日本画壇の代表的作家に依頼されたという。戦時下なのに出品されている16点のうち、戦争画は2点だけであった。堂本印象「如意輪観音」が目立つ位置に展示されているが、それよりも目を引いたのが上村松園「晩秋」。松園の代表作の一つとされ、画集類にもよく掲載されている。徳岡神泉「若松」も特色が出ていて面白かった。
久しぶりに美術展を見たという満足感が得られた。しかし、天王寺駅からの往復に長時間、歩かなければならない。元気なころはそれも楽しかったが、今は苦痛である。夜、就寝後に左足が痙攣を起こし、激痛に襲われた。気楽には訪館できない。4月からの「日本国宝展」は大混雑だろうし、諦めた方がよさそうだ。
2025年3月10日(月)トレフィラヌス研究
シェリング『第一草案』(Erster Entwurf)の邦訳(松山寿一訳)を読了。イエナ大学における最初の講義のための草稿である。第一部「自然がその根源的所産においては有機的であることの証明」、第二部「無機的自然の諸条件の演繹」、および第三部「有機的自然と無機的自然の相互規定」から構成されており、訳書では第一部だけが翻訳されている。「無制約者」(das Unbedingte)はいかに認識されるかといった形而上学的な議論が延々と続くのでうんざりする。訳者による解説(p.148)によれば、本書で体系全体を構築する方法が「進展」(Evolution)の概念であったという。Richards(2002)によれば、この進展の概念から独特の生物進化論が説かれているという。
Gambarotto(2017)によれば、本書でシェリングは繰り返しキールマイヤーを引用し、その説に基づく動物分類を提唱しているという。ここにもキールマイヤーの影響の強さがうかがえる。
2025年3月8日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。
2025年3月7日(金)内科医
昼前に隣町の福岡内科へ。前回、4ヶ月ごとの血液検査があったが、その結果は良好で問題ないとのことであった。ついでにスーパーに寄るつもりだったが、吹きさらしのシニアカーでは寒さで身が縮む。降圧剤と整腸剤を受け取り、一目散に帰宅した。
2025年3月6日(木)トレフィラヌス研究
昨日から、シェリング自然哲学の邦訳(松山寿一訳)通読を再開。『世界霊』(Weltseele)の抄訳(『宇宙霊』)を読了。今回も細部の不可解な部分は素通りして、トレフィラヌス『生物学』の理解に必要と思われる個所に注目した。「序言」(Vorrede)では、機械論(Mechanismus)は有機体論(Organismus)に包摂され、両者の対立は消滅するという。
Richards(2002)によれば、下記の文で始まる「序言」の一節で生物進化論が唱えられているという。「もしもすべての有機体の段階的連続が同一の有機組織の漸次的発展によって形成されたことを示せるとすれば、少なくともその証明のための一歩が踏み出されたことになろう。p.75改変」(Es wäre wenigstens Ein Schritt zu
jener Erklärung getan, wenn man zeigen könnte, daß die Stufenfolge aller
organischen Wesen durch allmähliche Entwicklung einer und derselben
Organisation sich gebildet habe. 旧全集Ⅱ348)。
本論は第一部「自然の第一の力について」(Über die erste Kraft der Natur)と第二部「普遍的有機体の起源について」(Über den Ursprung des allgemeinen Organismus)で構成され、第一部では無機的自然が扱われている。第二部で有機体論が説かれ、次のようにいう。「生命の積極原理は特定の個体に特有でありえず、創造全体に広がっており、あらゆる個体を自然の共通の息吹として貫いている。p.131改変」(Das positive Prinzip des Lebens
kann daher keinem Individuum eigentümlich sein, es ist durch die ganze
Schöpfung verbreitet, und durchdringt jedes einzelne Wesen als der
gemeinschaftliche Atem der Natur. Ⅱ503)。第二部の最終部分(p.147, Ⅱ567)では、遍在する磁気が特定の受容体にしか作用しないように、遍在する生命原理も特定の受容体だけに作用するという。共通の生命原理も各有機体の構成要素によって個性化する。これを消極的原理と呼んでいる。
キールマイヤー1793年講演録を絶賛し、「未来世代は明らかにこの講演を新しい自然史の時代の幕開きと見なすだろう。p.145」(eine Rede, von welcher an das
künftige Zeitalter ohne Zweifel die Epoche einer ganz neuen Naturgeschichte
rechnen wird. Ⅱ565)という。シェリングの有機体論がキールマイヤーの影響下で形成されたことが示唆される。
2025年3月2日(日)文楽見送り。シーラカンスの映像
一昨日、「文楽友の会」会報が届いた。4月公演「義経千本桜」の配役を見て三部構成のどれを観に行くか考えた。千歳太夫が切を勤める第三部「吉野山」は楽しめるはずである。しかし、終演が8時半、帰宅は10時になる。今では通常、9時に就寝するので、夜、遅くなるのが不安である。費用のことも考えて、今回は見送ることにした。
夜、9時からのNHKスペシャル「幻のシーラカンス王国」を見る。眠気を抑えて画面に見入った。集団になって隠れ家に潜むシーラカンスの映像など、感動的であった。番組の最後、シーラカンスの生息域にもプラスチックなどのゴミが流れてくる映像に愕然とした。
2025年3月1日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。3ヶ月ごとの体力測定の後、いつものメニューをこなす。帰宅後、シニアカーで隣町のスーパーへ。今後の天候を考えると、本日、買い物をしておく必要がある。疲労感はあるものの、無事に過ごすことができている。体調良好ということか。
2025年2月28日(金)医療費
還付申告書作成のため、まず医療費の計算に取り組んだ。しかし、昨年一年間の領収書と明細書を整理しただけで終わってしまった。なにをしても、すぐに疲れてしまう。文献を読む能力は(多分)衰えていないと思うのだが、体力、気力の衰えがはなはだしい。
2025年2月27日(木)整形外科
朝、三日市町駅筋の田中整形外科へ。隣の薬局で骨粗鬆症の薬を受け取って帰宅。それだけなのに、今日もまた、なにもできない。
2025年2月26日(水)散髪
朝、散髪のため外出。寒波は過ぎ去ったとはいえ、依然として寒い。散髪後に遠出する気力もなく、そのまま帰宅。それでも疲れ切ってなにもできない。
2025年2月23日(日)トレフィラヌス研究
シェリング『イデーン』(『考案』)「序説」の邦訳(松山寿一訳)を読了。とうてい、理解できたとはいえないが、シェリング哲学を極めることが目的ではなく、トレフィラヌス『生物学』を理解するためなので、ま、いいだろう。
『生物学』(1802)の「まえがき」(Vorrede)には、「全ての自然研究の最終目的は、我々が自然と呼んでいる巨大な有機体(grosse Organismus)が永遠に規則的な行動を維持している仕組みを明らかにすることである」(p.v)と述べている。シェリング有機体論の影響が明瞭である。ところが、その直後(p.vi)に、本書執筆のための作業を8年前から始めたとある。昨年7月12日のジャーナルに書いたことだが、『イデーン』(1797)の発行年とは時期が合わない。
『生物学』の「序論」(Einleitung)には『イデーン』と『第一草案』が引用されている(p.33n & p.54n)。「まえがき」と「序論」がシェリング自然哲学の影響下で執筆されたことは間違いない。しかし通常、「まえがき」と「序論」は本論を書き終えた後で執筆される。『生物学』第1巻(1802) 本論の分類、第2巻(1803)の分布、 および、第3巻(1805)前半の化石についての大量の研究論文を収集して読みこなし、体系的に整理して執筆するにはかなりの時間を要する。その作業を8年前、すなわち1794年に始めたというのは納得できる。そのきっかけはキールマイヤーの1793年講演録(1793)であった可能性が高い。トレフィラヌスは『生物学』第1巻と第2巻の 本論を執筆した後でシェリング自然哲学に出合い、自らの作業を理論化したのではなかろうか。Gambarotto(2017)の主張に引きずられてシェリング自然哲学の影響を過大評価していたかもしれない。『生物学』の本論にシェリング自然哲学がどこまで影響しているのだろうか。その点に留意して『生物学』を読んでいきたい。
2025年2月22日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。帰宅後の疲労感はほどほどだったが、寒さで身も心も縮んでしまう。
2025年2月21日(金)寒波
一昨日午後の降雪は土や樹木の上に残っているが、道路からは消えている。今後の寒波や通院の状況を考慮すると、本日を逃すと1週間は買い物に行けない。昼に外気温5度の中をシニアカーで隣町のスーパーへ。無事、帰宅したが、一日分のエネルギーを使い果たした気分である。
2025年2月19日(水)トレフィラヌス研究
1週間前から断続的にRichards(2002)を読んできたが、ようやく第3章と第8章のシェリング自然哲学論を読み終えた。著者によれば、有機体論は『イデーン』(1797)執筆の最終段階で着想されたものである。『イデーン』本文には有機体論が登場せず、「序説」(Einleitung)に記されているだけであるという。『世界霊』(1798)の「序説」の最後に「本書は『イデーン』の続編ではない」と記されていることを文字通りに受け取るべきであるという。『イデーン』(『考案』)の邦訳者、松山寿一も訳書の「解説」で、「これが『考案』そのものよりはむしろその後の著作への序説となっている」(p.341)と指摘している。
『イデーン』「序説」の最終節に登場する「自然は見える精神であり、精神は見えない自然である」(Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein.) はよく知られている。リチャーズによると、アレクサンダー・フンボルトはこの自然に精神があるという思想に感動し、『南アメリカ旅行記』を執筆する動機になったという。後にチャールズ・ダーウィンは『南アメリカ旅行記』に感動し、南米への旅を願うようになった。間接的にではあるが、シェリングはダーウィンにも強い影響を及ぼしていたことになろう。
さて、リチャーズによると、有機体論三部作の『世界霊』(1798)、『第一草案』(1799)、および『草案序説』(1799)は短期間に執筆されて十分な吟味を経ておらず、論理の飛躍もあり、互いに矛盾した主張も放置されているという。たとえば、ブルーメンバッハの形成衝動を生気論として非難する一方で、新たな説明原理として高く評価しているという。
第8章の最後に生物進化論が取りあげられている。『世界霊』では明白に生物進化論が説かれている。それは有機体論に基づくもので、普遍的有機体である自然は絶対的存在へ向けて「進展」(Evolution)をし続けるが、それに伴って構成要素の種も「進展」(Evolution)をしていくという。同時代のエラズマス・ダーウィンやその孫のチャールズ・ダーウィンの進化論とは全く異質なものであった。また、これは発生前成説の用語であった“Evolution” を「生物進化」の意味で用いた最初の例であろうという。『第一草案』には生物進化論を否定していると読める所があるが、これはエラズマス・ダーウィン『ゾーノミア』(1794-96)の進化論を批判していると解釈すべきであろうという。
第9章の「まとめ」(Conclusion: Mechanism, Teleology,
and Evolution)ではアリストテレス以来の哲学を簡略にたどり、カントは目的論が不可欠な生物について科学が成立しえないと主張した。それに対してシェリングは、有機体論(organism)によって生物と無生物とを含めた科学体系を樹立しようとしたという。その有機体論は科学研究に基づくものではなく、当時、流行していたロマン主義と個人的生活環境から生まれたものであったという。生活環境が思想形成に決定的な影響を及ぼすというのが、本書全体を貫く著者の立場である。
2025年2月15日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。帰宅後の疲労感はほどほどだったが、文献に取り組むのは無理だった。
2025年2月13日(木)トレフィラヌス研究
Richards(2002)を桃大図書館に返却する前にシェリング自然哲学についての議論だけでも読んでおきたいと、月初めから取り組め始めた。しかし、シェリングの自然哲学はフィヒテの自我論を基礎にしており、フィヒテの主張をそのまま受け継いでいるところもある。ひとまずRichards(2002)を脇に置き、岩崎武雄などの邦語文献でフィヒテ自我論とシェリング自然哲学について勉強しなおしてきた。本日からRichards(2002)のシェリング論に取り組みなおすことになった。
同書の第3章と第8章がシェリング自然哲学に当てられている。第3章では最初の自然哲学書『イデーン』(1797)と最後の自然哲学書『草案序説』(1799)が取りあげられ、、第8章では『世界霊』(1798)と『第一草案』(1799) が取りあげられている。
2025年2月10日(月)入金
昼前にバスで河内長野駅前へ。カードの引き落とし日なので、どうでも出かけなければならない。さいわい、寒さも少しは和らいできた。帰りはタクシーを利用したので帰宅後の疲労も軽くて済み、文献に取り組むことができた。
2025年2月8日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。今期一番の寒さではなかろうか。早朝は雪という予報ははずれたが、土の上に雪が残っていた。夜中に雪が降ったのであろう。道路には雪が無いので、ゴミ出しもデイサービスの送迎もいつも通りであった。この寒さを乗り切ることが今の最大の課題である。
2025年2月6日(木)内科医
とにかく寒い。とはいえ、降圧剤が切れるので隣町の福岡内科へ行かねばならない。昨日も昼前にシニアカーで出かけかけたが、突然、かなりの降雪となったので中止した。本日は雪の心配が無さそうなので、電熱チョッキにカイロ、コートなど、できるだけの防寒仕度で出かけた。帰宅後はぐったりして、なにもできない。
2025年2月2日(日)恵方巻き
テレビのニュースでは東京に雪の恐れがあると騒いでいたが、当地では夜の雨が朝のうちに止んだので、昼前に巻寿司購入のためシニアカーで隣町のスーパーへ出かけた。店は同じ思いの客で混雑していた。節分に特定の方角を向いて巻寿司を食べるという風習は、大阪に来た翌1978年の節分で初めて知った。今では関東にも広がっているらしいが、東西で文化の違いのある方が面白い。
2025年2月1日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューを問題なくこなす。帰宅後の疲労感もほどほどであった。体調は良いようだ。
2025年1月29日(水)散髪
朝、散髪に外出。家を出る時は雪がちらついていたが、まもなく止んだ。散髪後は久しぶりに難波へ。といっても駅ビルの外へ出ることはなく、地下街のユニクロで買い物をしただけ。それだけでも一仕事した気分である。
2025年1月28日(火)エルゴノミクスマウス
左腕にまだ違和感が残っているというのに、右腕にも異変を感じ始めた。このままではマウスが使えなくなり、パソコンが利用できなくなる。ネットで検索すると、腱鞘炎を防止するエルゴノミクスマウスがあるという。早速、有線で手ごろな価格のエレコム製品をアマゾンで購入した。マニュアルはネットで見よとなっているが、とにかく使い始めてみた。まだ慣れないが、本当に腱鞘炎防止になることを強く願っている。
2025年1月25日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。本日は帰宅後もかなり動くことができた。
2025年1月24日(金)トレフィラヌス研究
ここ数日、体調不良が続いていたが、本日は文献に取り組むことができた。『キールマイヤー論集』(2021)に掲載されている「1793講演録」の英訳を一気に読了。細部の検討にはドイツ語原文を参照するとしても、英文で通読する方がはるかに楽である。
「講演」では長い挨拶の後、本論の最初の部分で、生物の特徴は定常状態を保つことにあるという。これはトレフェラヌスが『生物学』の冒頭でそのまま受け継いでいる論点である。「講演」ではこれをもたらす力として5種の力を列記するが、後の議論に登場するのは、ハラーに由来する「感覚力」(Sensibilität)と「興奮力」(Irritabilität)、それとブルーメンバッハの「形成衝動」に由来する「生殖力」(Reproductionskraft)の3種の力である。この3種の力のバランスによって生物界の諸現象を統一的に説明しようとする。講演の最終部分では、それを人生、さらには社会にまで広げている。壮大な試みであった。
「講演」では系統発生に言及していない。したがって、いわゆる「発生反復説」を明示的には説いていないが、これを含意しているという解釈も可能であり、科学史家の見解が分かれている。しかしこの件に議論が集中するのはキールマイヤーの本意ではあるまい。「講演」は「生物学」成立に向けた重要な一歩と評価すべきであろう。
2025年1月18日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。いつものメニューをこなす。ただし右膝の軽い痛みが続いているので、一部の運動は制限した。テレビで得た知識によると変形性膝関節症である。なんとか悪化を止めたい。
2025年1月17日(金)トレフィラヌス研究
当面は『キールマイヤー論集』(2021)に集中するつもりでいたが、3月までに桃大図書館に返却すべき図書が数冊あることを思い出した。Richards(2002)などを優先しなければならない。
2025年1月15日(水)トレフィラヌス研究
昨日、アマゾンから届いた下記の洋書に着手した。年金生活の中で7千円の出費はつらいが、キールマイヤーについて語るには不可欠と判断した。
Lydia Azadpour and Daniel Whistler, eds., Kielmeyer and the
organic world: texts and interpretations. Bloomsbury Academic, 2021. pbk,
2022.
巻頭の第1章「編者序論」によれば、キールマイヤーに関する初の英語の単行本である。「英語圏のキールマイヤー・ルネサンス」(this anglophone Kielmeyer-renaisance. p.2)のきっかけになったのが、Andrea Gambarotto, Vital forces, teleology and organization. Springer
2018. であるという。同書は前年の2017年にハードカバーで刊行されているので、2017年と記載すべきではなかろうか。
2025年1月13日(月)トレフィラヌス研究
昨日と違って体調良好。電熱チョッキを着用することもなく、朝から機嫌よく動いていた。手元にあるキールマイヤー二次文献を調べてみた。DSB第7巻(1973)に項目があり、コールマンが執筆しているが、NewDSB(2008)には立項されていない。Coleman(1973)以降、キールマイヤー研究に進展は無いとみなされていたのである。グールド『個体発生と系統発生』(1977)ではキールマイヤーにさしたる関心は向けられていない。1793年の講演録が文献欄に記載されているが、実際にはColeman(1973)を読んだだけではなかろうか。
2025年1月12日(日)寒波
とにかく寒い。暖房を効かせ、ヒートテックの下着と靴下、さらに電熱チョッキで身を覆い、要所にカイロを張り付けていても、身も心も凍る。文献に取り組める状態ではない。夜になって少しは心身が動くようになったので、年末から放置していたアマゾンへの発注を済ませ、3日分のジャーナルを書いている。
2025年1月11日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。前日の午前は積雪のため休業したとのことだが、本日は送迎に問題はなかった。
2025年1月10日(金)内科医
夕刻5時前に隣町の福岡内科へ。数日前から降圧剤が切れていたが、雨雪のためシニアカーでの通院が無理だった。今朝も道路に積雪があったが、昼までに溶けたのでシニアカーで行くことができた。一昨日の外出の疲れもあるのだろう、帰宅後は疲れ果てていた。
2025年1月8日(水)文楽劇場「忠臣蔵八段目・九段目」
2時15分開演の初春公演第2部へ。朝、当地では雪がぱらついていたので交通機関に不安があったが、通常通りに往復することができてほっとした。
床直下の席なので、八段目の「道行」では清治に率いられた五丁の三味線が耳元で鳴る。わくわくする。「山科閑居」の前半が千歳太夫・富助、後半が藤太夫・燕三。たっぷり楽しんできた。
観客席は満席にはほど遠いものの、半分以上は埋まっていたと思う。かなりの客が第3部「本朝廿四孝・四段目」を観るために居残っていた。残念ながら今の自分にはそれだけの体力がない。4月公演も3部構成で「千本桜」の通し。第1部「大物浦」、第2部「すしや」、第3部「吉野山」。さて、どれを観に行こうか。
2025年1月5日(日)トレフィラヌス研究
Richards(2002)でキールマイヤーの項を読んだ後、キールマイヤー生前唯一の刊行物である1793年の講演録をネットからプリントアウトした。当時のドイツ語文をひげ文字で読むのはつらいと思っていたが、google books では不完全ではあるがテキスト化も可能であった。トレフィラヌスは直接、およびシェリングを介してキールマイヤーから決定的な影響を受けていた。トレフィラヌス研究にはブルーメンバッハとキールマイヤーの理解が欠かせない。当面は、キールマイヤー1793年講演録を読み取っていきたい。
2025年1月4日(土)デイサービス
午前中はデイサービス「ポラリス大矢船」で運動機能訓練。本日が事業所の仕事始め。といっても土曜日なので世の中はまだ正月気分。住宅地では依然として路上駐車が目立つ。スタッフによると一般道路は走りやすく送迎が楽だとのこと。本日は運動量をほんの少し増やしてみたが、帰宅後の疲労はほどほどであった。
2025年1月2日(木)ホームページ更新
我がホームページの更新に取り組んだ。昨年分のジャーナルを新規のページに移動。ついでに「芝居」のページに加筆し、少々早いがトップページの年齢を修正しておいた。
2025年1月1日(水)ジャーナル執筆
穏やかな元旦を迎えた。本日は電熱チョッキを着用することなく過ごすことができた。早朝、数通の年賀状が届いた。業者からのほか、昨年、年賀状仕舞いの挨拶を送った方からも届いている。どう対処すべきなのか悩んだが、何もしないことにした。
午後は31日付のジャーナルに「今年は何をしたか」を書き、本日付で「今年は何をするか:生物学史に思う」を執筆した。公開のジャーナルに書くことで自分の考えをきちんと整理することができ、意欲を高めることにもなる。
夜はNHKEテレの「ウィーン・フィル、ニューイヤーコンサート」で新年気分を味わっている。
2025年1月1日(水)今年は何をするか:生物学史に思う
既存の生物学史には重大な過失が二つある。一つは遺伝学の成立をメンデル個人の天才的着想とみなし、まともな研究がなされてこなかったことである。メンデルは伝統的な植物雑種の研究をしていただけであった。このメンデル神話については拙著「総説・メンデルは遺伝学の祖か」」(2016)でも指摘しておいた。他の一つの過失は、「生物学史」といいながら19世紀初頭に「生物学」が成立した経過をなおざりにしてきたことである。その現れがトレフィラヌス『生物学』が無視されてきたことといえよう。とはいえ、業績の積み上げを要請される現役世代の研究者には、膨大なトレフィラヌス『生物学』に取り組む余裕はないだろう。ここは業績など気にしない世代の出番と考えたい。
アリストテレス以来の生物学通史を書くことを、定年退職後の大きな目標としていた。その場合、多くを二次資料に頼ることになり、時間もかかる。これを諦めて、トレフィラヌス『生物学』を中心に生物学成立の経過をまとめておきたい。その前後の生物研究の状況を語ることで、通史に代わるものが書けるのではないかと期待している。何年掛かるか分からない。寿命、体力、それと視力しだいだが、なんとか完成させたいと思う。
2024年12月31日(火)今年は何をしたか
2月末に紀要論文「ジョフロア=サンチレールの生物学思想:『プランの一致』の歴史的意義」を投稿し、掲載誌が10月に刊行された。4月からはジョフロアの背後に見え隠れする「ドイツ自然哲学」の生物学に取り組んだ。その過程でトレフィラヌス『生物学』のことを知り、6月末からは同書の研究に集中することになった。当初は「9月末脱稿を目指す」としていたが、とんでもない。年単位で取り組まなければならないテーマであった。
高齢になると心配なことの一つが、判断力が低下し、研究者としても、晩年のジョフロアのように、迷惑な存在になってしまわないかということである。11月に頭部裂傷で救急搬送されたおりのCTスキャンによると、脳の状態は85歳とは思えない若々しさであるという。自信をもって科学史研究に取り組むことができる。問題は、体力低下と緑内障による視力障害だが、今のところ日常生活に支障はない。あまり気にせず、研究を進めていきたい。